ブログ/お知らせ Knowledge
Webサイト制作の要件定義とは何か、その目的と考え方
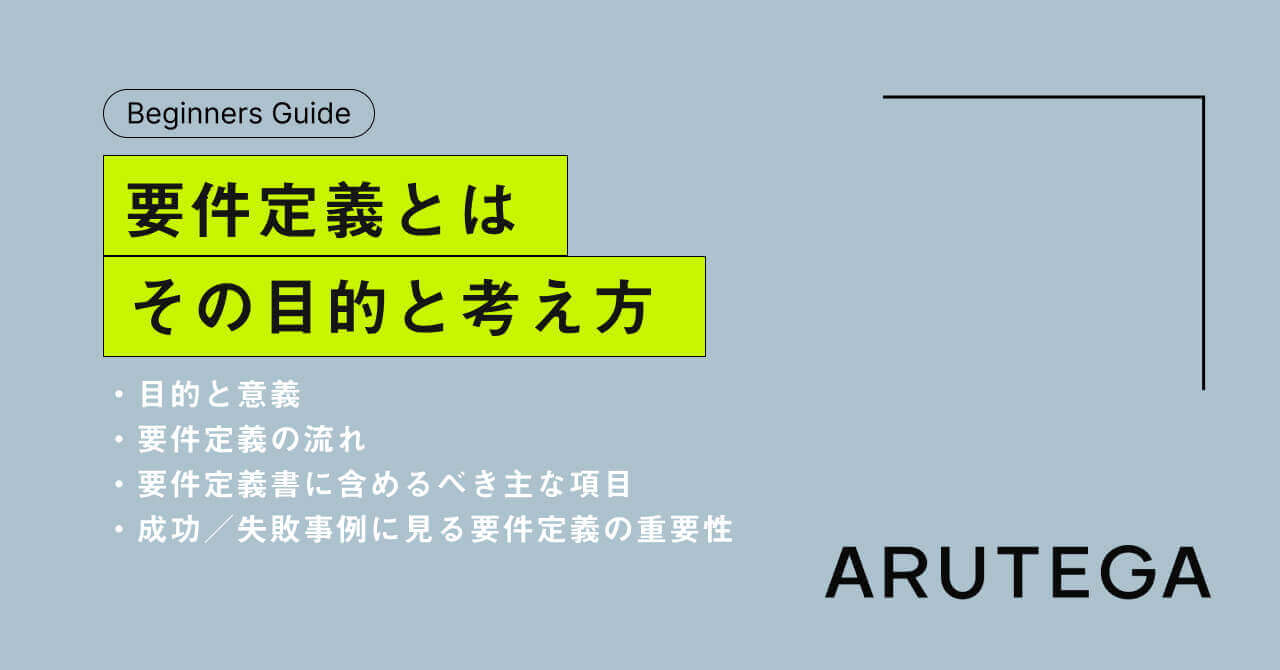
ARUTEGA(アルテガ)の平尾です。
普段はコーポレートサイトやブランドサイトの制作をメインにしているクリエイティブディレクターです。
さて、Webサイト制作を始めるに当たって、一番最初の難関は要件定義です。
この記事ではWebサイト制作を16年している私が考える要件定義の進め方と陥りやすいポイントを要約してます。
これからコーポレートサイトやブランドサイト制作を発注しようと考えているWeb担当の方に参考になるはずです。
要件定義の丁寧さと緻密さでサイト制作の成果が変わることは言うまでもありませんが、Web制作会社に知識がないとすっ飛ばしてデザインに着手したりすることがあります。
そういった、『何のためにWebサイトやデザインを作るのか』を明確にするためにぜひご一読ください。
要件定義とは何か、その目的と意義
要件定義とは、Webサイトに求められる機能や目的を明確にする作業で、プロジェクト成功の土台を築く重要な工程です。
しっかりと行うことで関係者間の認識を揃え、後の工程を円滑に進められます。
Webサイト制作における要件定義とは、作ろうとしているWebサイトにどんな役割や機能が求められるかを明確にすることです。
その目的は、関係者全員がサイトの目標や必要な要件について共通認識を持ち、プロジェクトを円滑に進めることにあります。
要件定義は、言わばサイト制作の土台づくりであり、この段階での認識共有がWebサイト制作の成功を左右すると言っても過言ではありません。
要件定義を行うことで、プロジェクトの方向性が具体的になり、関係者間で合意形成を図りやすくなります。
例えば、Webサイトのターゲット設定(誰に向けたサイトか)、サイトの目的(何を達成したいか)、必要な機能要件(盛り込みたい機能)や非機能要件(表示速度やセキュリティなどの品質面)といった事項をこの段階で洗い出します。
これにより、後から「聞いていた話と違う」といったトラブルを避け、全員が同じゴールを目指して動き出せるのです。
このように、要件定義はWeb制作プロジェクトの羅針盤となるものであり、しっかりした要件定義がWebディレクションの成否を握ると言えるでしょう。
要件定義の流れ
要件定義の流れをこの順番でお伝えしていきます。
Webサイトの要件定義は、現状分析から始まり、仮説の立案、合意形成を経て、最終的に文書化する流れで進みます。
各段階を丁寧に進めることで、要件の抜け漏れを防ぎ、確実な計画を策定できます。
現状分析(現在の課題やニーズの把握)
まずは現状分析からスタートします。
現在Webサイトをお持ちの場合は、そのサイトの課題点やアクセス解析結果、ユーザーからのフィードバックなどを洗い出します。
新規にサイトを制作する場合でも、市場や競合の動向、自社のサービス内容などを調査し、現状のニーズを明確にします。
この段階で、サイト制作の背景や目的を改めて確認し、解決すべき課題や達成したい目標を整理します。
仮説立案(解決策とサイトコンセプトの検討)
現状分析で得られた情報を基に、どんなWebサイトにすれば課題を解決し目標を達成できるか、仮のプランを立てます。
例えば、サイトのコンセプトや大まかなサイトマップ(構成)、必要になりそうな機能リスト、コンテンツ案などをここで考えます。いわば要件のたたき台を作る段階であり、この仮説が後の議論の土台となります。
合意形成(関係者との要件すり合わせ)
仮説としてまとめた計画案を基に、関係者と話し合って合意形成を図ります。
関係者には、サイトの依頼主(クライアント)や社内の関連部署、開発・デザイン担当者などが含まれます。
各方面からの意見や要望を踏まえて計画をブラッシュアップし、全員が「これで行こう」と納得できる形に要件を固めます。
このプロセスを経ることで、後になって認識のズレが発覚するリスクを減らせます。
文書化(要件定義書の作成)
最後に、合意した内容を正式な要件定義書として文書化します。
要件定義書には、決定したサイトの目的やターゲット、サイトマップ、機能一覧、デザイン方針、スケジュール、予算などが整理されて記載されます。
文書化しておくことで、後からチーム内で「言った言わない」の食い違いを防ぎ、プロジェクトの指針として参照できるようになります。
また、この要件定義書が次の設計や開発工程への引き継ぎ資料ともなります。
要件定義書に含めるべき主な項目
要件定義書は、要件定義の結果を整理した文書です。ここにはプロジェクトの背景や目的から具体的な機能一覧、デザイン方針、スケジュール、予算に至るまで、Webサイト制作計画に必要な項目が網羅されます。
背景・目的
まず、プロジェクトの背景と目的を明記します。
なぜこのWebサイトを制作するのか、そのきっかけや経緯、抱えている課題などを背景として記載します。
そして、サイトを通じて何を実現したいのかという目的をはっきりさせます。
背景と目的を示すことで、プロジェクトの大前提や最終的なゴールを関係者全員で共有できます。
ターゲット(対象ユーザー)
次に、Webサイトのターゲット(想定ユーザー層)を定めます。
誰に向けたサイトなのかを具体的にイメージし、年齢層、性別、地域、ニーズなどの観点で定義します。
必要に応じてペルソナ(具体的な架空のユーザー像)を設定すると、より明確にターゲット像を共有できます。
適切なターゲット設定は、コンテンツやデザインの方向性を決める指針となります。
サイトマップ(構成)
サイトマップは、Webサイトのページ構成やナビゲーションを示した一覧です。
要件定義書では、想定されるページ(ホーム、製品紹介、問い合わせ等)がすべて洗い出され、どのような構成で配置されるかを示します。サイトマップを明らかにすることで、必要なページ漏れを防ぐとともに、全体の情報構造を関係者が共有できます。
機能要件(必要な機能)
機能要件とは、Webサイトに実装すべき具体的な機能の一覧です。
例えば、「お問い合わせフォームを設置する」「商品検索機能を提供する」「会員登録とログイン機能を持たせる」といった具合に、サイトが備えるべき機能をすべてリストアップします。
それぞれの機能について、詳細な条件や挙動(例えばフォーム項目や検索フィルターの種類など)を補足しておくと尚良いでしょう。
機能要件を明確にしておくことで、開発段階での齟齬を防ぎ、必要なシステム開発の規模や難易度も把握できます。
非機能要件(品質要件)
非機能要件は、サイトの機能以外の品質に関する要件です。例えば、ページ表示速度の目標値やサーバーの稼働率、安全性(セキュリティ対策)、SEO(検索エンジン最適化)に関する方針、スマートフォン対応(レスポンシブデザイン)、アクセシビリティ(障害のある方への配慮)などが該当します。こうした品質面の要件も予め定めておくことで、デザインや開発の際に指針となり、サイトの完成度を高めることができます。
デザイン方針・要件
デザインに関する要件も明確にします。サイトのトンマナ(雰囲気)やブランディング方針、使用する色やフォントの制約、ロゴ・画像素材の扱い、UI/UX上の留意点など、デザイン面で守るべきガイドラインを定めます。例えば「シンプルで信頼感のあるデザイン」「自社ロゴのカラーを基調にする」等の方針を示しておけば、デザイナーとの認識合わせがスムーズになります。
スケジュール
プロジェクトのスケジュール(進行計画)も重要な項目です。
サイト公開までの大まかなタイムラインを示し、主要なマイルストーン(例:要件定義の完了時期、デザイン提出日、テスト期間、公開日など)を設定します。スケジュールを明確にしておくことで、関係者全員が同じペースで進捗を管理でき、遅延リスクにも早めに対処できます。
予算
最後に、プロジェクトに投じられる予算を記載します。
全体の予算額や、その内訳(制作費、システム開発費、マーケティング費用など)が決まっていれば盛り込みます。
予算を明確にすることで、要件とコストのバランスをとる指標となり、計画段階で費用対効果を検討しやすくなります。
また、予算内で実現可能な範囲を見極めることで、要求が無制限に広がってしまうのを防ぐ効果もあります。
成功/失敗事例に見る要件定義の重要性
要件定義がプロジェクトの成否を左右すると言っても過言ではありません。
しっかり行ったケースではスムーズに進み成功しやすく、逆に不十分だとトラブルが続出して失敗につながることもあります。
ここでは、成功例と失敗例を通じて要件定義の重要性を見てみましょう。
成功例:要件定義が功を奏しスムーズに進行した事例
とある企業のWebサイトリニューアルプロジェクトでは、着手前に時間をかけて綿密な要件定義が行われました。
プロジェクトチームは依頼元の部署と何度も打ち合わせを重ね、サイトの目的やターゲット、優先すべき機能要件を明確化しました。
その結果、デザインや開発に移行してからの手戻りがほとんど発生せず、スケジュール通りにサイトを公開することができました。
また、サイト公開後も「狙ったターゲットからの問い合わせ件数が向上した」など、当初の目的通りの成果を上げています。このプロジェクトが成功した背景には、初期段階で要件定義書を作成し関係者間で認識を揃えたことが大きく寄与しています。
失敗例:要件定義不足が招いたプロジェクトの混乱
一方、別のWebサイト新規構築プロジェクトでは、要件定義を簡略に済ませてしまったために問題が発生しました。
サイト制作を進める中で「こんなはずではなかった」という認識ズレが次々と明らかになり、開発途中で仕様変更や追加要望が相次ぎました。
本来は計画に無かった機能の追加やデザイン修正が重なった結果、当初の予算とスケジュールは大幅に超過してしまいました。
最終的にサイト自体は公開にこぎつけたものの、想定より時間もコストもかかり、肝心のユーザーにも使いづらいサイトとなってしまいました。
この失敗の大きな要因は、プロジェクト開始時に十分な合意形成と要件の洗い出しができていなかったことにあります。
初めにしっかり要件定義を行っていれば避けられたはずの手戻りであり、要件定義の重要性を痛感させる例と言えます。
まとめ(適切な要件定義がWebサイト成功のカギ)
適切な要件定義を行うことが、Webサイト制作の成功に直結すると言っても過言ではありません。
初めての方でもポイントを押さえて丁寧に進めれば、後の工程が格段に進めやすくなり、成果につながるWebサイトを作ることができます。
要件定義は地味な作業に思えるかもしれませんが、Webサイト制作における最重要ステップの一つです。
闇雲に制作を始めるのではなく、最初にしっかりと要件定義書を作成しておくことで、デザインや開発を安心して進められます。
もし要件定義の進め方に不安がある場合は、社内の関係者と十分に話し合うことはもちろん、必要に応じてWeb制作の専門会社や経験豊富なWebディレクション担当者に相談するのも有効です。
適切な要件定義こそが、あなたのWebサイトプロジェクトを成功に導くカギです。ぜひ本記事の内容を参考に、納得のいくWebサイトを完成させてください。
よくある質問をまとめました
Q. 要件定義と設計(基本設計)の違いは何ですか?
A. 要件定義は「何を実現したいか」「どんな機能が必要か」といったプロジェクトの内容や条件を決める工程です。一方、設計(基本設計)は、決まった要件をもとに「どう実現するか」を具体化する作業です。要件定義ではサイトの目的や機能の一覧を洗い出し、設計ではそれらを実装するための画面遷移やデータベース設計、システム構成など技術的な詳細を詰めていきます。簡単に言えば、要件定義は計画づくり、設計はその計画を形にする段階と考えるとよいでしょう。
Q. 要件定義書は必ず作成しなければいけませんか?
A. 厳密に「必須」という決まりはありませんが、プロジェクトの規模に関わらず要件定義書の作成を強くおすすめします。口頭や頭の中だけで合意したつもりでも、文書として残しておかないと認識違いや漏れが発生しやすくなります。小規模なサイト制作であっても、簡易的なメモでもよいので要件を書き出しておくことで、後から「聞いていない」「想定と違う」といったトラブルを防げます。
Q. 要件定義は誰が行うべきでしょうか?
A. 要件定義は、プロジェクトの責任者や企画担当者が中心となって行うケースが多いです。社内にWebサイト制作の担当者(Webディレクションを担う人)がいればその人がリードし、関係部門からのヒアリングを経て要件をまとめます。自社にノウハウがない場合は、Web制作会社のディレクターやコンサルタントに支援を依頼することも有効です。重要なのは、最終的な決定権を持つ人と現場の担当者が協力して進め、全員の合意を得ることです。
まとめ:目的に合わせて、適正な費用とパートナーを選ぼう
最後に、自社の目的に合わせて適正な費用配分と依頼先を選ぶことが大切です。
サイトの目的や求めるクオリティによって、かけるべき予算や選ぶべきパートナーは異なります。価格だけにとらわれず、自社のニーズに合った相手を選びましょう。適正な相場観を持って信頼できるパートナーと進めていけば、きっと納得のいくWebサイトが完成するはずです。
弊社ではブランディングサイトを多く構築しております。
デザインに強く、SEO対策までをワンストップにできるデザイン会社をお探しの方は弊社ARUTEGAまでご連絡ください。








