ブログ/お知らせ Knowledge
Webサイト制作ツール3選:WordPress・STUDIO・Canvaの徹底比較とプロ仕様の選び方
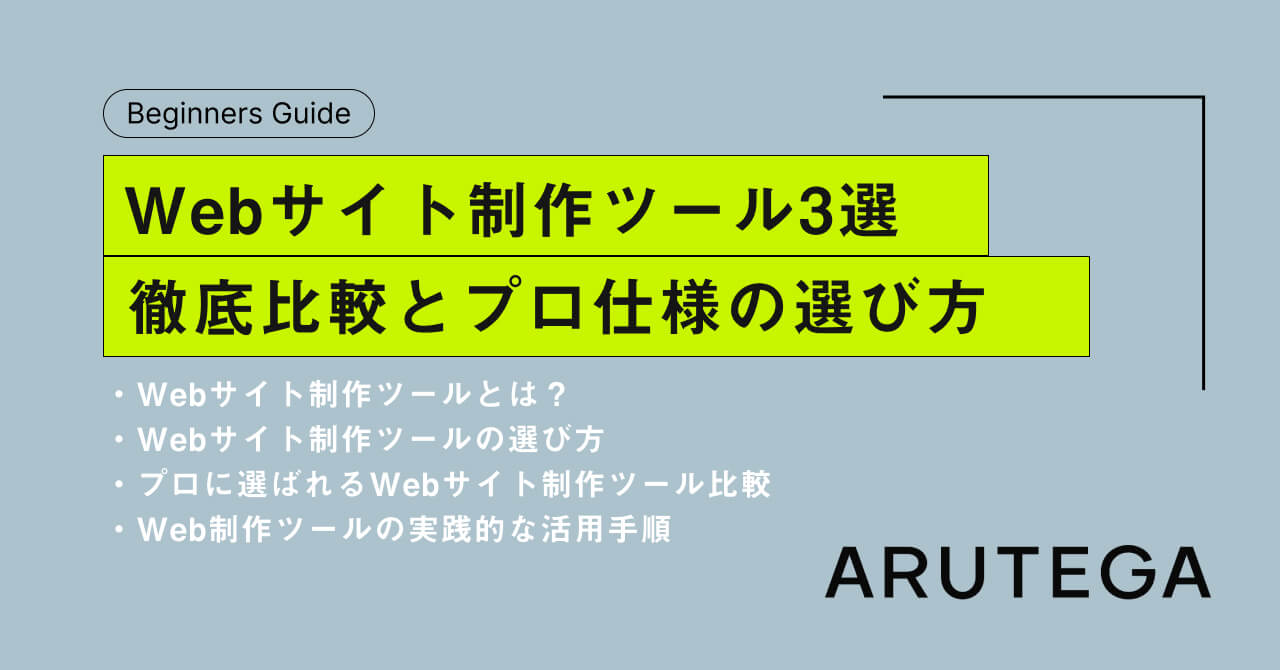
ARUTEGAの代表の平尾です。
この記事ではWebサイト制作における制作ツールについて紹介しています。
Webサイト制作ツールを使えば、専門知識がなくても魅力的なサイトを作成可能です。
本記事では、CMSの王道WordPress、ノーコード開発のSTUDIO、デザイン特化のCanva Webサイトを比較し、目的別の選び方や制作手順、ビジネス活用のポイントまでを解説します。
初心者からプロまで役立つ内容です。
Webサイト制作ツールとは?
この記事での『Webサイト制作ツール』とは、プログラミングの知識がなくてもWebサイトを設計・構築できるソフトウェアやサービスの総称をさしています。
従来はHTML/CSSを手作業でコーディングしたり、専用の開発ソフトを使ったりする必要がありました。
しかし近年は、専門スキルがなくても直感的な操作でプロ並みのサイトを作れるツールが数多く登場しています。
Webサイト制作ツールの定義と種類
一般に、Webサイト制作ツールにはいくつかの種類があります。
まずCMS(コンテンツ管理システム)と呼ばれるものがあり、ブログ記事やページなどのコンテンツを一元管理しやすくする仕組みです。
WordPressはその代表例で、世界中で広く利用されています。
次に、ホームページビルダー型のサービスがあります。
例えばWixやJimdo、今回取り上げるSTUDIOなどは、ブラウザ上で操作できるクラウド型のサイト構築サービスです。
また、デザインツール系ではCanvaのように、グラフィックデザイン感覚でページを作成できるものも登場しています。
このように、コードを書かずにサイトを作れる「ノーコードツール」から、自分で細部を作り込める高度なCMSまで、用途やスキルレベルに応じた様々なツールが存在します。
従来型とクラウド型の違い
Webサイト制作ツールは、大きく「従来型」と「クラウド型」に分けることができます。
従来型とは、自分のPCにソフトをインストールしたり、自前のサーバーにCMSを導入して運用するタイプです。
例えば、サーバーにインストールして使うWordPress(オープンソース版)は従来型と言えるでしょう。
従来型の利点は、自社サーバー上で自由度高くカスタマイズできる点や、オフライン環境でも作業できる点です。
しかし、その分初期設定や保守管理に専門知識が要求されるケースが多くなります。
一方、クラウド型のWebサイト制作ツールは、インターネット上のサービスとして提供されるものです。
ユーザーはブラウザからログインして使用し、ソフトのインストールやサーバー管理は不要です。
STUDIOやCanvaのWebサイト作成機能はこのクラウド型に該当します。
クラウド型のメリットは、手軽に始められて常に最新の機能が使えることです。
サーバーやソフトのアップデートはサービス提供側が行うため、ユーザーはコンテンツ作りに専念できます。
また、クラウド上にデータがあるためチームでの共同編集や、場所を選ばない作業も容易です。
デメリットとしては、サービスに機能が依存するためカスタマイズの自由度が限定されることや、月額料金などのランニングコストが発生する点が挙げられます。
Webサイト制作ツールの選び方
数多くのWebサイト制作ツールが存在する中で、自社に最適なものを選ぶにはいくつかの観点を押さえておく必要があります。
ここでは、サイトの目的や規模、使う人のスキルレベルに応じた選定基準や、無料プランと有料プランの違いについて解説します。
目的別に見る選定基準
まず、サイトの目的によって適したツールは異なります。
例えば、ブログやニュースなど定期的にコンテンツを更新するオウンドメディア型のサイトを作るなら、記事管理やSEOに強いWordPressが有力な選択肢です。
一方で、企業のコーポレートサイトやサービス紹介サイトのようにデザイン性を重視しつつ比較的静的なコンテンツが中心の場合、ノーコードで美しいデザインが実現できるSTUDIOが適しています。
また、ポートフォリオサイトやイベント告知のランディングページなど、比較的シンプルな1ページ構成で良い場合はCanvaのWebサイト機能を使えば短時間で魅力的なページを公開できます。
また、必要な機能もツール選定の重要なポイントです。
問い合わせフォームやブログ機能、EC(通販)機能などを求める場合、プラグインで機能拡張できるWordPressが適しています。
逆に「とにかくシンプルで見栄えの良いサイトが作れればよい」という目的であればSTUDIOやCanvaで十分でしょう。
初心者〜プロまでの対応幅
WordPressは機能が豊富な反面、初心者にはややハードルが高い部分もあります。一方、STUDIOは初心者でも扱いやすく、デザインの自由度が高いためプロのデザイナーからも評価されています。Canvaは最も手軽に使えますが、本格的なサイト制作にはあまり向きません。
無料と有料の違い
多くのWebサイト制作ツールには無料プランと有料プランが存在します。
WordPress自体は無料ですが、サイト公開にはレンタルサーバーや独自ドメインの費用(年間数千〜数万円程度)が必要です。
STUDIOやCanvaなどクラウドサービスも無料プランから開始できますが、サイトURLがサービス側のサブドメインとなる、ページ数やアクセス量に制限があるなどの制約があります。
ビジネス用途では独自ドメインの利用や安定した運用のため、有料プランへの移行が必要になるでしょう。
一般に有料プランでは機能やサポートが強化され、より多くの素材や分析ツールが使えるなどメリットがあります。
無料で試して手応えを掴んだら、必要に応じて有料版にアップグレードし、信頼性やブランディング効果を高めるのがおすすめです。
プロに選ばれるWebサイト制作ツール比較
ここでは、プロフェッショナルからも高い支持を得ている3つのWebサイト制作ツール「WordPress」「STUDIO」「Canva Webサイト」について、それぞれの特徴を比較してみましょう。
それぞれ異なる強みを持つツールなので、自社のニーズにマッチするポイントを確認してください。
WordPress:拡張性とCMSの王道
WordPress(ワードプレス)は世界中のWebサイトのおよそ4割が利用すると言われるほど圧倒的シェアを誇る代表的なCMSです。
オープンソースで開発され、ブログから企業サイト、ECサイトまであらゆる種類のサイト構築に対応できる柔軟性を持ちます。
その秘訣は豊富な拡張性にあり、プラグインを追加することで問い合わせフォームやSNS連携、ネットショップ機能まで必要な機能を後付けできます。
また無数のテーマ(デザインテンプレート)が公開されており、見た目のカスタマイズも自由自在です。
WordPressはコンテンツ管理もしやすく、ブログ記事の投稿などを担当者自身で行いやすい仕組みになっています。
ただし自由度が高い分、ソフトウェアの更新やセキュリティ対策など運用上のメンテナンスはユーザー側で対応する必要があります。定期的なアップデートやバックアップ作業を怠らないようにしましょう。
膨大なユーザーコミュニティのおかげで困ったときに情報を得やすい点も含め、拡張性と安定性を重視するならWordPressはまさに王道の選択肢です。
弊社ではWordPressの制作を特に得意としています。実績はこちらからご覧ください。
STUDIO:ノーコード×高品質デザイン
STUDIO(スタジオ)は日本発のノーコードWeb制作プラットフォームです。
コーディング不要で直感的に操作でき、デザインの自由度が非常に高い点が特徴です。
ブラウザ上のエディタでテキストや画像をドラッグ&ドロップし、スタイルを細かく調整するだけで、プロが作ったような洗練されたWebページを制作できます。
用意されているテンプレートを活用すれば初心者でも短期間で公開までこぎつけられます。
サーバー設定も不要で、作ったサイトはそのままSTUDIO上で公開できます。
STUDIOはコードを書かずにピクセル単位のこだわりを実現できるため、デザイナーなどプロからの評価も高いツールです。
ただし、会員機能やデータベース連携など複雑なシステムには不向きで、基本的にはコーポレートサイトやLP、ポートフォリオなど中小規模サイト向けと考えると良いでしょう。SEOの基本設定やレスポンシブ対応もプラットフォーム側でサポートされており、公開後の運用も比較的簡単です。
Canva Webサイト:ビジュアル重視のクリエイター向け
Canva Webサイトは、デザイン作成ツールCanvaでWebページを作れる機能です。
チラシや資料を作るような感覚で、1ページ完結の簡易Webサイトをデザインできます。
操作はドラッグ&ドロップ中心で、専門知識が一切なくてもおしゃれなページが数分で完成します。
自己紹介用のポートフォリオやイベント告知ページ、SNSのプロフィールに載せるリンク集ページなどに活用されており、豊富なテンプレートから好みのデザインを選んで写真やテキストを差し替えるだけで見映え良く仕上がります。
現状Canvaで作成できるのは1ページサイトのみで、複数ページから成る本格的なサイトには不向きです。
また、見出しタグの挿入ができない・レスポンシブ表示の微調整ができない等、SEO面での細かな制約もあります。
そのためテキスト中心よりは画像やイラストを多用したシンプルな構成に適しています。
無料版ではサイトはCanvaのサブドメイン上で公開されますが、Canva Proに加入すれば独自ドメイン接続も可能です。
手軽さとデザイン性を両立できる反面、機能面では限定的なので、Webに不慣れなクリエイターや個人事業主が手早くオンライン名刺代わりのページを作る用途に適したツールと言えるでしょう。
Web制作ツールの実践的な活用手順
実際にWebサイト制作ツールを使ってサイトを作る際の、大まかな手順を押さえておきましょう。
どのツールを使う場合でも、共通して以下のようなステップで進めると効率的です。
サイト構成と目的設計
まずはサイトの目的と大まかな構成を設計します。
「何のためのサイトか」「誰に何を伝えたいのか」を明確にし、必要なページの一覧を洗い出しましょう。
例えば企業サイトであれば「ホーム」「サービス紹介」「会社概要」「お問い合わせ」、個人ポートフォリオなら「プロフィール」「作品ギャラリー」「連絡先」といった具合です。このように事前にサイトマップ(構成図)を作っておくことで、後のデザイン作業やツール選定がスムーズになります。
https://arutega.jp/make-website-guide07-definition/
テンプレート選択とカスタマイズ
次に、使用するツール上でデザインの骨組みを作ります。
WordPressであればテーマ、STUDIOやCanvaであればテンプレートから、サイトの目的に合ったレイアウトを選びましょう。
選択したデザインを自社のブランドに合わせてカスタマイズします。ロゴやメイン画像を差し替え、ブランドカラーやフォントを設定します。不要なセクションは削除し、新たなブロックを追加して必要なコンテンツを盛り込みます。
デザインの統一感や余白のバランスに気を配り、PCだけでなくスマホ表示でも崩れがないかプレビューで確認しながら調整しましょう。
コンテンツ作成とUI調整
デザインが固まったら、各ページに掲載するコンテンツを作成して配置します。
伝えたいメッセージを整理し、わかりやすく魅力的な文章を書くよう心がけます。適宜見出しや箇条書きを用いて読みやすくし、重要なキーワードは太字で強調すると効果的です。
同時に、ボタンやリンクの配置などUI(ユーザーインターフェース)の調整も行います。
ナビゲーションメニューのリンク切れがないか、問い合わせボタンは目立つか、といった点をチェックしましょう。
スマホでの操作感も確認し、必要であれば画像圧縮などでページの表示速度を改善します。
公開・改善・運用
すべてのコンテンツを入れ終わったら、サイトを公開します。
WordPressの場合はサーバーにアップロードしてドメインを設定し、STUDIOやCanvaの場合は「公開」ボタンをクリックすればインターネット上にサイトが表示されます。公開後は実際にアクセスして、レイアウト崩れやリンクエラーがないか入念にテストしましょう。
ただし、サイト公開はゴールではなくスタートです。
公開後はGoogleアナリティクスやサーチコンソールなどを活用して訪問状況をモニタリングし、得られたデータをもとにコンテンツの追加・改善を続けてください。こうした運用・改善の積み重ねにより、Webサイトはよりビジネスに貢献するものへ成長していきます。
制作ツールをビジネスに活かす応用戦略
最後に、Webサイト制作ツールを活用してビジネス成果を高めるための応用的なポイントを紹介します。
せっかく便利なツールでサイトを作ったからには、そのサイトをしっかり集客や売上につなげ、継続的に改善していくことが大切です。
SEOとの連携と最適化
制作ツールを使っても、SEO(検索エンジン最適化)の基本は同じです。
サイト公開前に以下の点を確認しましょう。
- タイトルタグ・メタディスクリプション: 各ページに検索結果に表示される適切なタイトルと説明文を設定します(主要キーワードを含める)。
- 見出しタグと画像ALT: コンテンツ内でh1やh2などの見出しを使い文章を構造化し、見出しに重要キーワードを含めます。また、掲載する画像には必ずALTテキスト(代替説明)を設定します。
- モバイル対応と表示速度: スマホでレイアウトが崩れていないか確認し、画像圧縮などでページ表示を高速化します。
WordPressであればSEOプラグイン(例:Yoast SEO)を使って細かな最適化が可能ですし、STUDIOやCanvaでもページごとにタイトルや説明文の設定は行えます。基本を押さえておけば、どのツールで作ったサイトでも大きな差はありません。
解析・改善ループの回し方
Webサイトは公開して終わりではなく、公開後にデータを解析して改善することが成功のカギです。
アクセス解析ツールで「どのページがよく見られているか」「離脱率の高い箇所はどこか」などをチェックし、課題に応じてコンテンツや導線を改善します。例えば直帰率の高いページは内容や誘導を見直し、問い合わせを増やしたければフォームへの動線を強化するといった具合です。
分析(Check)→ 改善策の実行(Act)→ 再度計測(Plan/Do)というPDCAサイクルを継続的に回し、サイトのパフォーマンス向上に繋げましょう。
外注と内製の使い分け
近年のツール普及により、Webサイトを内製(自社で制作)しやすくなりました。
内製のメリットは、コストを抑えてスピーディーに公開できる点です。
ツールの使い方に慣れれば自分たちで素早く更新作業も行えるため、特にスタートアップや小規模事業者ではまず内製でサイトを立ち上げるケースが増えています。
一方で、企業のコーポレートサイトなどプロに外注した方が効果的な場合もあります。
経験豊富な制作会社に依頼すれば、洗練されたデザインや高度なSEO対策が施されたサイトに仕上げてもらえるでしょう。
内製と外注を組み合わせることも可能です。
例えば初期構築だけプロに任せて以降の運用更新は自社で行う、あるいはまず内製で小さく始めて軌道に乗った段階でプロにリニューアルを依頼する、といった使い分けも有効です。
自社のリソースや目的に応じて、最適な方法を選びましょう。
まとめ
今や誰でもアイデア次第で魅力的なWebサイトを作れる時代になりました。WordPressのような拡張性抜群のCMS、STUDIOのようなノーコードでデザイン性の高いサービス、Canvaのように手軽さ重視のツール、それぞれに異なる強みがあります。
大切なのは自社の目的やリソースに合ったツールを選び、上手に活用することです。
どのツールを使う場合でも、サイトの目的設計やコンテンツの質、公開後の運用改善が成功の鍵を握ります。この記事のポイントを参考に、ぜひ貴社のWebサイト制作・運用にお役立てください。
適切なツール選びと戦略的な運用によって、Webサイトはきっとビジネスの強力な味方になるはずです。
「どの制作ツールを使えば良いか分からない」「プロに任せた方が良いか悩んでいる」そんな場合は、ぜひお気軽にご相談ください。
お客様の目的に合わせて最適なツール選定からサイト制作・運用までサポートいたします。ご相談やお見積もりは無料です。








